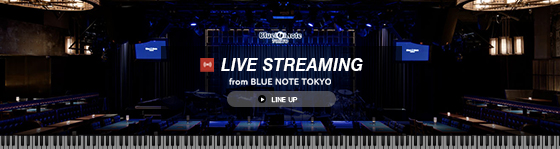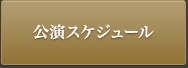2013 1.10 thu. - 1.11 fri.
NICK WATERHOUSE
artist NICK WATERHOUSE

原田和典のBloggin' BLUE NOTE TOKYO
このところ、アナログ・レコードの生産が伸びているそうです。ジャケットからレコード盤を取り出して、溝に指紋をつけないようにそっとターンテーブルに置き、針を載せる。それは、CDを聴くときとはまったく別種の"儀式"です。
今年はもっとアナログ・レコードが脚光を浴びるといいなあ、と思っていたところ、とてつもない「アナログ感」を感じさせるアーティストがアメリカからやってきました。ネオ・ヴィンテージ・ソウルの新星、ニック・ウォーターハウスです。この時代、"45回転のシングル盤でデビュー"というだけでも嬉しくなりますが、とにかく彼の曲作りは、「よくぞまあ、ここまで'50~'60年代のサウンドを取り入れたものだ」と驚いてしまうほど、あの時代へのリスペクトに溢れています。
ブルース、ロカビリー、R&B、テックス・メックス等の要素が反映された曲が、次々とプレイされます。ニックのヴォーカルはちょっと飄々とした感じで、'60年代初頭のディオンを思わせます。そしてギター・プレイは、太い音色と深いエコーで押しまくり、デュエイン・エディの"トゥワンギー・サウンド"を髣髴とさせる瞬間がありました。ニックはきっと、こうしたサウンドを復刻盤CDではなく、モノラルのアナログ・レコード、それもシングル盤を探して聴きまくっていたのでしょう。ただ往年の音楽を参考にするのではなく、その時代の空気までも今に蘇らせようという気迫が伝わりました。
バック・バンドも本当に、嬉しくなってしまう音を出していました。バリトン・サックス奏者はリズミカルなリフを繰り返し、テナー・サックス奏者はグロウル奏法も交えながら、まるでサム・ブテラのようなブロウを展開します。ピアニストは小型のキーボードも兼用していましたが、そこから出てくるオルガンの音がなんともチープで、ジョニー&ザ・ハリケーンズが好んで使っていたトーンを思い起こさせます。
ふたりの女性シンガーのモデルは、レイ・チャールズのレイレッツでしょうか、アイク・ターナーのアイケッツでしょうか。タンバリンを揺らしながらのコーラス、そしてニックのヴォーカルに対する合いの手、すべてがかっこよくサマになっていました。
もちろん出世作「Some Place」をはじめ、主要レパートリーは、すべてといっていいほど味わうことができました。カヴァー曲では「Ain't There Something Money Can't Buy」に驚かされました。ヤング=ホルト・トリオ(初代ラムゼイ・ルイス・トリオのベース奏者とドラマーが独立して組んだバンド。ラムゼイよりもR&B寄りの音楽性で人気を博した)のブルース的な代表曲を、ニックはサックス・セクションをフィーチャーしながら、あくまでも小粋に仕上げていきます。
ニックはこれが初来日です。人気を確立したベテランの安定と貫禄も素晴らしいものですが、これからが楽しみな気鋭のステージに接する快感は、また格別です。公演は本日もあります。ぜひどうぞ!
(原田 2013 1.10)