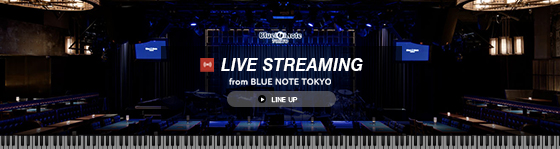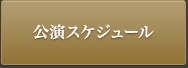2016 8.6 sat., 8.7 sun., 8.8 mon.
JOHN CALE
artist JOHN CALE

原田和典のBloggin' BLUE NOTE TOKYO
熱狂的だったパンチ・ブラザーズ公演の余韻が残る「ブルーノート東京」に、昨日からアーティスティックなロック・サウンドが響き渡っています。
'60年代から第一線で活動するレジェンド、ジョン・ケイルの登場です。英国ウェールズ出身ですが、芸術家アンディ・ウォーホルとの出会いやヴェルヴェット・アンダーグラウンドでの活動から、"ジョンの音を聴くとニューヨークの風景が浮かんでくる"というファンも少なくないのではないでしょうか。
2016年の彼は、鬼才ドラマー、ディーントニ・パークスを含むバンドを率いて、幅広い年代にわたる代表曲を、"今これをプレイするなら、このアレンジしかないだろう"という感じの音作りでプレイしています。
オープニングの「Hedda Gabler」から、会場は大いに沸きます。ジョンは椅子に座り、ステージ前方にあるキーボードを弾きながら歌います。深みのある声、聴きとりやすい言葉。曲によってフェンダー・ローズ風、パイプ・オルガン風など、キーボードの音色設定を細かく変えながらのパフォーマンスです。そしてべースのジョーイ・マランバも指弾きでファンキーなフレーズを奏でると思ったら、弓を用いて幻想的な響きをも生み出します。コントラバスならともかく、エレクトリック・ベースで弓弾きを聴かせる奏者は世界的にも希少なのではないでしょうか。ギターのダスティン・ボイヤーも、あるときはタイトなカッティングを披露し、またあるときは流麗な和音(コード)で酔わせ、さらにまたあるときは楽器を膝の上に置いてラップスティール・ギターを弾くときのように音程をスライドさせるなど変幻自在。しかもバック・コーラスでは、"ジョンがもうひとりいるんじゃないか"といいたくなるほどよく似た声でハーモニーをつけるのですから、驚きです。
"TECHNOSELF"としても評判を集めているディーントニ(活動を停止したロック・バンド"マーズ・ヴォルタ"での活躍については言うまでもないでしょう)はシンバルなし、スネア+ハイハット+バスドラ+タム1個+サンプラーという独自のセットで重量感あるリズムを生み出します。とにかく全員が万能のプレイヤーであり、ステージ上はたった4人なのに、大型バンドのように分厚く、スケール感豊かなサウンドが広がっている・・・それが今回の公演なのです。
'80年代からのレパートリーである「Thoughtless Kind」、2005年のアルバム『Black Acetate』に入っていた「Wasteland」、'73年の意欲作『Paris 1919』からの「Hanky Panky Nohow」(後半、バンドが一丸となってジャム・セッション風に即興するところは、まさに"ライヴの醍醐味"でした)などが、次々と登場してはファンを喜ばせます。ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの歴史的名盤からは「Sunday Morning」と「I'm Waiting for the Man」が取り上げられました。そこでは当時24歳の故ルー・リードがメイン・ヴォーカルをとっていました。それを現在74歳のジョン・ケイルが、コクのある歌声で丁寧に丁寧に歌い上げるのです。しかも手の届きそうな距離で!公演は8日まで続きます。
(原田 2016 8.6)
Photo by Tsuneo Koga
coming soon